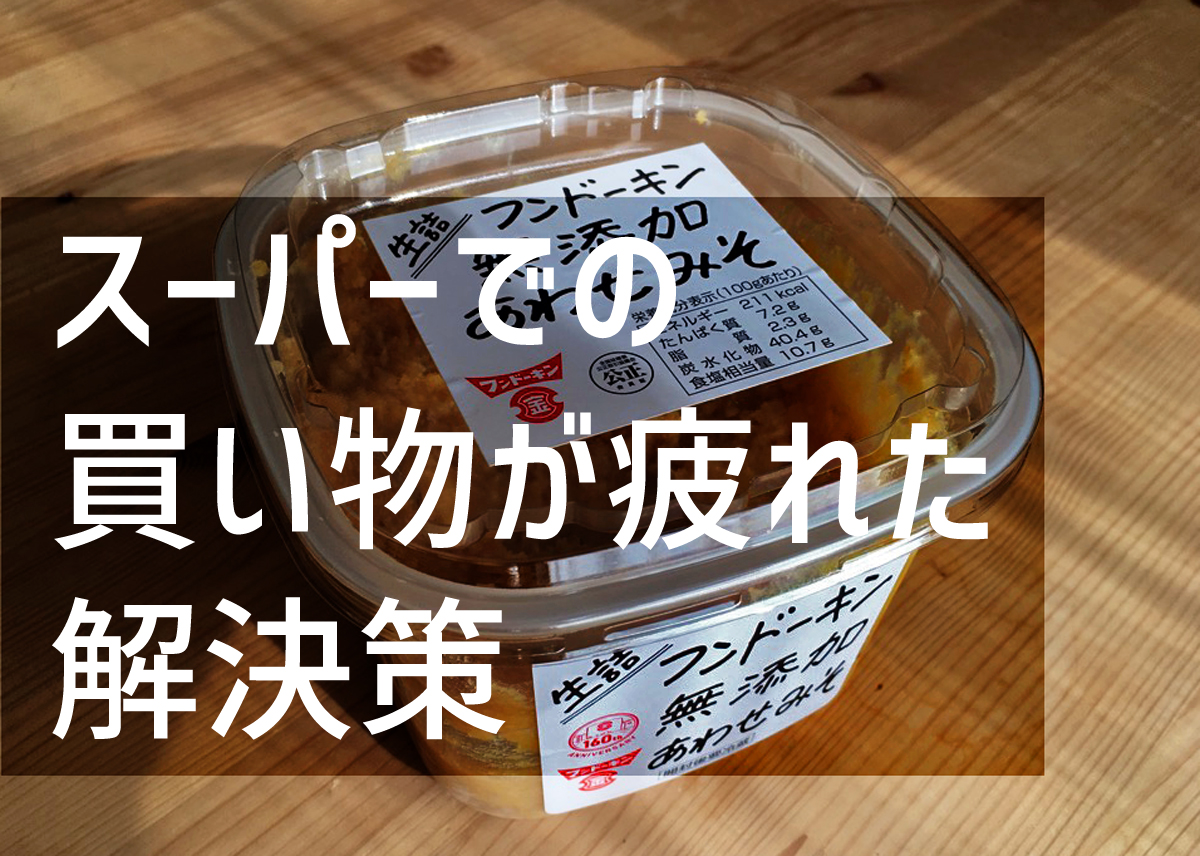古い家に引っ越してきて当初、庭は荒れ放題でした。

地植えで花を植えたい!
固い地面を掘って地植えで花苗を植えてみたのですが育ちが良くありません。
ですので土を耕してみました。
耕してみたら異物が沢山出てきましたよ!
地植えで花を植えようとしたら土中から出てきたもの
- コンクリートガラ
- 石
- コガネムシの幼虫
本記事では、これらの異物を除去して植物を植えるまでをご紹介いたします。
土を耕した場所
土を耕した場所のビフォー写真がこちらです。

この倉庫を撤去してカチカチの土をひたすら掘り、土をふるい、異物を取り除き、培養土や牛糞を混ぜ込みながら耕していきます。
するとこんな感じに植物が育つようになりました。(下はアフター写真です。)
-800x571.jpg)
草花が育つとやっぱり嬉しいですね。
土の掘り方
まず、庭の土を掘ります。
土を掘る道具道具
土を掘る道具はこの2つの道具を使いました。
土を掘る道具
- 備中鍬
- シャベル

備中鍬というのは写真の通り刃が分かれているものです。

土の掘り方
初めて土を掘ろうとした時にシャベルを土に差し込みました。

掘れない!
しかし、私の力が弱いからなのかシャベルではカチカチになっている土を上手く掘る事ができませんでした。

ですのでシャベルではなく備中鍬を使い土を砕いて掘り起こす事にしました。

固い地面を砕くにはシャベルよりも備中鍬の方が作業が進みました。
ある程度の範囲(50センチ×70センチくらい)の土を備中鍬で掘り起こしてから、シャベルで土をすくう方が作業がスムーズにいきました。
3カ所掘ったのですが穴の大きさはこんな感じです。
- 幅50センチ×長さ4メートル×深さ50センチ
- 幅50センチ×長さ3メートル×深さ50センチ
- 幅30センチ×長さ6メートルちょっと×深さ40センチ
道路沿いのスペースを2カ所、駐車場側のスペース1カ所、計3カ所掘りました。
掘った土の中から出てきたものは?
コンクリートガラと石

道路沿いのスペース2カ所からはコンクリートガラと石が沢山出てきました。

コンクリートガラとは建物を解体する時に出るコンクリート破片のことです。
ザクザクとガラや石が出てきましたが土が粘土質でなかった事とガラスやタイルの破片は埋まっていなかったので少しホッとしました。
掘り起こした土をふるう

コンクリートガラと石の入った土はふるう事にしました。
ふるう専用の道具を持っていなかったのでキッチンで使っていたステンレス製のザルを使いました。
土を掘ってはふるい、掘ってはふるいを繰り返します。簡単に書いていますが、これが時間も体力もかかりむちゃくちゃ大変な作業でした!
(毎日ではなかったのですが)3カ所の掘り起こし作業を一人で終えるのに3週間程かかってしまいました。
出てきた石とガラは一カ所にまとめ耕した土に混ざらないようにします。
大きなガラや石は花壇のふちにでも再利用しようと思い処分はせずとっておく事にしました。

コガネムシの幼虫
駐車場側の植栽スペースにはこれでもか!というくらいのコガネムシの幼虫が出てきました。
幼虫はクリーム色でアルファベットの「C」の形に丸まっていました。
※コガネムシの幼虫の写真が出てきます。虫が苦手な方は画像をスルーしてくださいね。

コガネムシは夏頃(7~9月)に土中に卵を産みます。その卵から孵化した幼虫が地中で過ごしてから成虫となり、また卵を産むので幼虫自体は一年を通して土中にいます。この幼虫は植物の根を食べてすぐに枯らしてしまうので大変やっかいです。
私は見つけ次第、一匹づつ駆除していきました。
全部で20匹以上は出てきたと思います。
しかし、道路側の土中からは一匹もコガネムシの幼虫が出てきませんでした。
駐車場側の地面は駐車場拡張工事の際に土が少し柔らかくなっていたのでコガネムシが卵を産みやすかったのかなと思いました。
反対に、道路側の地面は長年倉庫が置かれていてコガネムシが卵を産みずらい環境だった、そして倉庫撤去後も一年以上更地でしたが地面が固かったのでコガネムシが卵を産むのに適した土ではなかったのかなと想像しました。(素人意見です)
培養土を投入するけど足りない問題
土を掘り起こし異物や幼虫を取り除いたところで培養土を投入しました。

素人なのでどのくらいの土を購入すればよいのか見当もつきません。
とりあえず近所の園芸店へ行き25リットルの培養土を4袋購入しました。
帰宅後に道路沿いの一カ所にまず土を投入したのですが全く足りません。
あわてて追加で2袋購入して追加投入するのですが深さがあるせいで全く足りませんでした。
今、振り返って考えてみると土の量が足りないのも当然です。

お恥ずかしい限り
土の量の計算方法
私が培養土を入れたい植栽スペースの大きさは、幅50センチ×長さ4メートル×深さ50センチでした。
なので、土の量を計算してみると下のようになります。
土の量の計算方法
面積(平方メートル)×土の厚さ(メートル)=容量(立法メートル)
容量(立法メートル)×1.000=容量(リットル)
容量(リットル)÷25リットル(培養土一袋の量)=必要な袋数
これに当てはめてみると、
1平方メートル×0.5メートル=1立法メートル
1立法メートル×1.000=1.000リットル
1.000リットル÷25リットル=40袋
25リットルの培養土が40袋必要!
全然足りないのも当然ですね。

こんな事も考えつかないくらいの適当さで庭づくりをしていました。
地面に穴を掘ったところを全て新しい土に変えようとするとお金も結構かかる事が分かります。
土を耕す(土を混ぜる)

掘った箇所の土を全て購入した培養土に出来れば良かったのですがお金もかかるのでちょっと迷ってしまいました。
最終的には掘った土が粘土質では無かったので混ぜて使う事にしました。
これも土を掘り起こす時に使用した備中鍬で混ぜました。
耕す(混ぜる)作業は土を掘る時に比べると力はかからず全然楽でした。
土の消毒について(失敗談)
本来は耕した方の土中に害虫や病原菌がいるかもしれないので土を消毒してから混ぜた方が良かったのですが、私は手抜きをしてきちんとした消毒はしませんでした。
耕した土を1週間程、地面の上に広げて太陽光にあてただけです。
途中で土をかき混ぜる事もしませんでした。

しかし、これが後の失敗につながりました。
コガネムシの幼虫を除去したつもりでしたが恐らく卵までは除去しきれていなかったようで、後で卵から成長したコガネムシに沢山の植物の根っこを食べられてしまいました。

不幸中の幸いだったのは掘った土を混ぜなかった事です。
3カ所の土を掘りましたが混ぜる事はしなかったので、コガネムシの被害が出たところは1カ所のみでした。
土の消毒方法
夏と冬で方法が異なります。土の異物は前もって除去しておきます。
夏
土に水を撒いて黒いゴミ袋をかぶせます。そのまま太陽光にあて消毒します。満遍なく太陽光があたるように時々土をかき混ぜます。(常に土は湿った状態を保たせます)
冬
土に熱湯をかけ寒さにさらします。満遍なく寒さにさらせるよう時々土をかき混ぜます。
※土を消毒する期間は数日で良いという意見もあれば3週間程という意見もあります。個人的には太陽光の強さや寒さの度合いなど季節によって期間を変えて良いのではと思いました。しっかりと暑さ寒さにさらして目で見えにくい虫の卵なども殺菌する事が大事なのではと思います。(素人意見です。)
根っこが食べられた植栽スペースは再度土を掘り起こしコガネムシの幼虫を駆除し、培養土や堆肥を入れて耕し直しました。
花苗を植えてみる
土を耕した場所に草花の苗を植えます。
最初はコキアを植え、その翌年にはセンニチコウなど、一年草を中心に植えてみました。
問題なく育ったので、その後は花苗を植え替える度に培養土や牛糞を混ぜて更に少しづつ土を変えていきました。

土に栄養がある状態の方が草花がより元気に育つという事も少しづつ分かってきました。
今ではこんな感じに草花が育つスペースに変わりました。

頑張った分、地植えにした草花が元気に育った時のうれしさは格別です。

コガネムシの幼虫に根っこを食べられていた植栽スペースでも草花が育つようになりました。
最後に
石だらけの庭に花を植えたくて土を耕してみましたが、3つの事が分かりました。
- 土の中にはコンクリートガラや石、コガネムシの幼虫が埋まっているかもしれない
- 土を耕す(掘る)作業は重労働
- 地植えをしたいなら土作りは大事
土を耕す作業はかなり体力を使います。

全身筋肉痛になるような重労働でした。
作業をする方は熱中症などに十分注意をして無理をしない範囲で行ってくださいね。
この記事が庭づくりをする方の参考になれば幸いです。
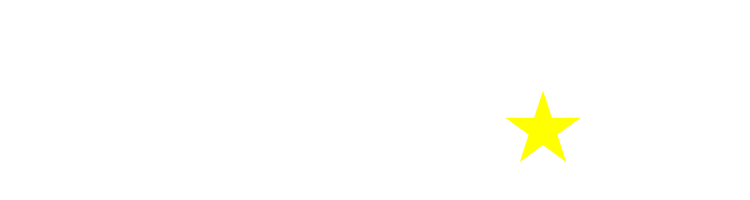
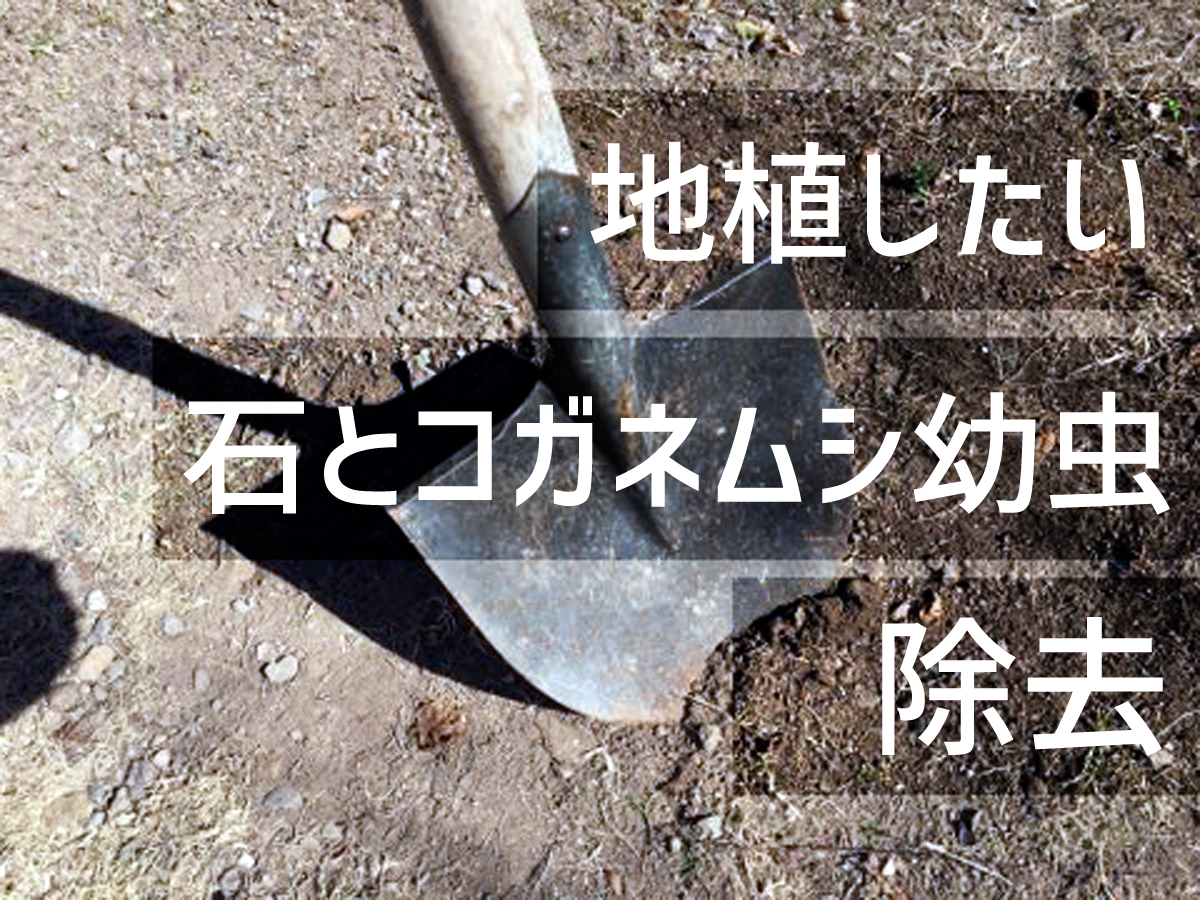
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a13d6df.f282dd51.2a13d6e0.b5fe3a95/?me_id=1209220&item_id=10002030&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhonmamon-r%2Fcabinet%2Fimg3%2Fw4580149745643.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a147a65.7d63d684.2a147a66.3a7a62c0/?me_id=1308194&item_id=10042511&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdcmonline%2Fcabinet%2Fa229%2F4580178915482.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a47c809.f56f6b7b.2a47c80b.c095e821/?me_id=1194164&item_id=10000009&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgardening%2Fcabinet%2Fyoudosenyoudo%2Fimg_3937.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a480464.2f724e21.2a480465.36f470e5/?me_id=1228244&item_id=10000046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fluxfort%2Fcabinet%2Fgtg%2Fd-51_w.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a47c809.f56f6b7b.2a47c80b.c095e821/?me_id=1194164&item_id=10000517&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgardening%2Fcabinet%2Fhiryousennyouhiryo%2Fdsc_2803.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)